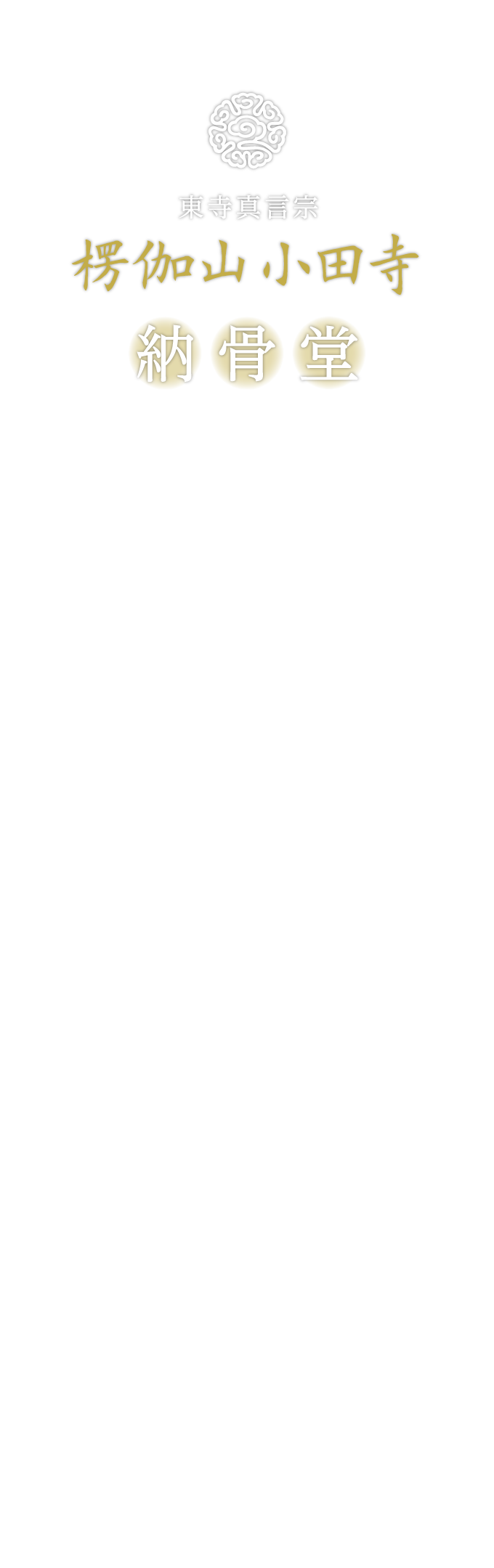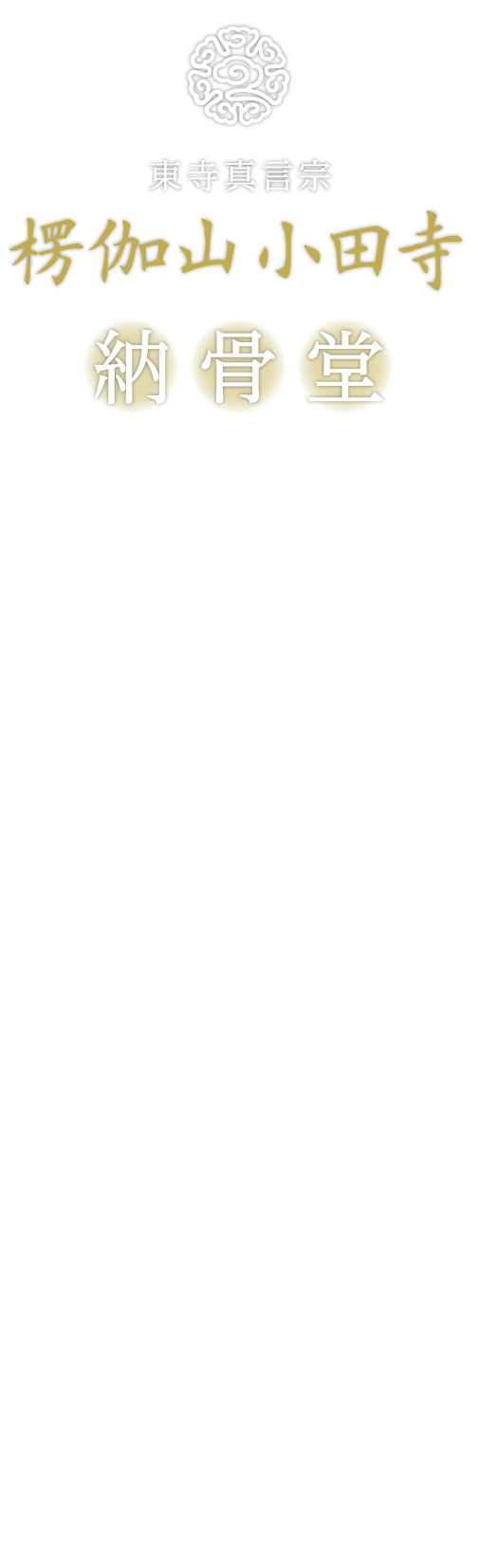※観音堂は桁行3間、梁行3間、寄棟造り、本瓦葺一尺角の面取柱の上に舟肘木をのせて軒桁をうけ、正面両端柱頭は和洋平三斗組となっている。 内陣は笇緑天井、須弥壇の来迎柱の平三斗組には彩色が残っているが現在来迎壁を取り外し舞良戸をとりつけ厨子形式に改造されている。
心安らぐ納骨堂

岡山県小田郡矢掛町の伝統あるお寺が運営する
心安らぐ納骨堂
天平12年(740年)創立の、伝統がある楞伽山小田寺が
岡山県の許可を得て運営する納骨堂です。
許可番号:岡山県指令備中局地第432号
いずれの宗旨・宗派でも構いません
宗旨や宗派に関係なくご利用頂けます。
ご遺骨の一時預かりの管理料不要
当山では、一時預かりにかかる管理料は一切不要です。
365日、いつでもお参りいただけます
境内には駐車場を完備しておりますので、
高齢の方や体の不自由な方も、365日いつでも安心してお参りいただけます。
安心・安全な管理体制
楞伽山 小田寺 納骨堂は、暗証番号と個別カギで管理されているため、
安心してご利用できます。

納骨堂での供養が選ばれている理由
近年、納骨堂での供養が人気を集めています。
新しくお墓を建てるは、予算の面で不安がある方も多いのが理由の一つです。
また、生活環境によっては自宅と墓地が遠く、頻繁にお墓参りができないこともあります。
さらに、遠くのお墓の管理が難しいことや、子どもたちに負担をかけたくないという思いも、
納骨堂を選ぶ理由になっています。
楞伽山 小田寺の納骨堂なら、
安心して大切な方を偲ぶことができます。

ご利用料金について

楞伽山小田寺納骨堂の利用料


永代供養等(合祀)の利用料


墓地の使用料
料金はご相談ください

〜永代供養で安心のご供養〜
相談承ります。ご事情によりご法要が難しい方に代わり、
責任をもってご供養を執り行います。
詳しいご案内はお気軽にお問い合わせください。

楞伽山小田寺 縁起
楞伽山小田寺 寺院縁起
天平12年(740年)4月8日、行基菩薩により創建。
法相宗にして本尊は当郡の氏仏であり当時小田郡最大の伽藍として人々の崇拝をうけていた。現在は真言宗。
延喜2年(902)益信僧正より伝法灌頂が行われ三密瑜伽の道場となる。
備中国観音霊場16番。

小田寺観音堂
矢掛町指定重要文化財 昭和37年指定
応安2年(1369年)神戸山城主床上小松秀清、
当山に帰依し七堂伽藍及び、寺家十二坊を建立し、庄園三十町を寄進する。
弘治元年(1555年)8月当村祭礼の夜、小田神戸山城、攻落され当山堂舎兵火にかかりことごとく鳥有に帰す。
落城の時、城主小田清隆再び神戸山城に帰城せんことを小田寺本尊に祈誓す。
永禄8年(1565年)神戸山城主小田隆清により当山々腹に再建す。
現在の堂は背後の堂山にあったものを後世移建したと伝えられている。
町内において最も古い建築で屋根の美しい幻配などよく、江戸初期様式を残している。
十一面千手観世音菩薩
矢掛町指定重要文化財 昭和37年指定
本尊の十一面千手観世音菩薩は鎌倉末期の秀作であり観音堂とともに、
昭和37年矢掛町指定重要文化財に指定されている。
像長1.5メートル、総丈1.73メートル。
光背は後補のものであり、作者は不明である。脇仏は不動明王、毘沙門天。

寺院概要
| 寺院名 | 楞伽山 小田寺 |
|---|---|
| 宗派 | 東寺真言宗 |
| 住職名 | 久保田 隆昭 |
| 所在地 | 〒714-1227 岡山県小田郡矢掛町小田819 TEL.0866-84-8728 |
主な行事
| 1月 | 年始祈祷 |
|---|---|
| 3月 | お彼岸供養(納骨堂・永代供養塔) |
| 8月 | お盆参り、お盆供養(納骨堂・永代供養塔) |
| 9月 | お彼岸供養(納骨堂・永代供養塔) |
| 11月 | 権現社大祭 |
| 12月 | 除夜の鐘 |
| 年数回開催 | 写経会 |
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせフォームに必要事項をご入力の上ご送信ください。
お電話でも受け付けておりますのでお気軽にTEL.0866-84-8728までご連絡ください。
お問い合わせフォーム
下記フォームにご入力の上、「確認する」ボタンを押してください。